モラフスキー・クルムロフへ、アルフォンス・ムハの《スラヴの叙事詩》を観に行ったのは、もう10年は前のことである。
ムハの生まれ故郷、イヴァンチツェから約10キロ。モラヴィア南西部を蛇行するロキトナー川がS字をえがく淵に位置することから、おそらくその地名がある。流れがくるっと曲がっているからクルムロフ──といわれるのも、あながち駄洒落というわけでもなく、語源学的にkrumm(曲がった)というドイツ語の形容詞によって裏打ちされている。
題名の「叙事詩」は、原語でepopej(エポペイ)という。当時、車をだしてくれた連れに「ところで、エポペイって何」と訊かれたものである。おいおい、日本人にチェコ語の語義を訊くのかと呆気にとられたものだ。日本での関心のほうが高い作品ということもあるが、現代語ではepos(エポス)という同義語のほうが普及しているという事情もある。いずれにせよ日常もちいられないから、要は好事家だけが知る語彙に属する。
それゆえ、人文系の科目に疎いひとには「スラヴ人のエポペイ」という題名が厳密に何を指しているのか、よくわからない。しかし連作を観覧しているうちに、ああなるほど、こういうことかな、とアイデンティティの来歴に想いを馳せる。あるいは、それがまたムハの意図でもあったかと思う。偉大な先人たるコメニウスにあやかって、ひろく民族のための視覚教材を企図したというところか。それだからこそ、教材が置かれるのは、あらたにチェコスロヴァキア民族の聖地となったプラハでなくてはならなかった。たぶん。芸術家としての野心も相応におおきかったとは思うが。
この大作が、画家本人の遺志によって、プラハ市に属するものとされたことは、したがって不思議ではない。実子のイジー・ムハによる画家の伝記にも、そのことが書いてある。ざっと訳してみれば──《スラヴの叙事詩》は1928年からプラハ市の所有物となったが、父[アルフォンス・ムハ]は贈与契約書のなかで、一般公開されることと、そして威厳をたもって安置されることと条件をつけた。ところが、それが執行されるべき期限を設定するのを忘れた。それでプラハ市庁は法的に拘束されることがなかったため、条件の履行はえんえんと棚上げ、先送りされることとなった。たしかに絵画はプラハの見本市の新産業会館にて厳粛に市民に公開され、そこからブルノの見本市会場に移送されたが、のちに一時的な避難場所として、プラハのナ・ストゥダーンツェにある学校のホールに追いやられ、さらに丸められたまま、戦争がはじまるまで22年ものあいだ、あちこちの倉庫を盥廻しにされた(Jiří Mucha, _Alfons Mucha_, Praha, 1999.)。
《叙事詩》はなんとか保護領時代を生きのびたものの、戦後まもなく統治者となった共産党中央としては、汎スラヴなどという時代錯誤の胡乱なイデオロギーを喧伝する「教材」が首都に鎮座することを看過できるわけがない。しかも、ベル・エポックに活躍したブルジョワ画家の作品ときている。なるべくひとの目にふれぬモラヴィアの僻村に作品を保管させることにしたのは、合理的であった。しかし作品が無事に遺されたという結果にかんがみれば、これでよかったのかもしれない。
画家の親族らをまきこんだ相続問題が横たわっていたにもかかわらず、大作は社会主義体制がおわったのちも、しばらくはモラヴィアの村にとどまった。それでも時代とともに価値観がおおきく変化するなかで、海外での人気も後押ししたのか、やがて文化財指定がかかり、それと前後して法廷でプラハ市庁の言い分がとおった。かくして2011年、《叙事詩》が首都にひきとられるときがやってきた。ドナドナの憂き目にあう絵画たち。人口6千人に満たない村が随一にして唯一ともいえる観光資源をむしりとられた。すでになんでも持っている、120万人の暮らすプラハに。
ところが、この2020年の師走である。疫病騒ぎも収まらぬ年の瀬に、《叙事詩》の所有権にかんする判決の報道があった。原告は、同様の訴訟をたびたび起こしてきた、作者の孫であるジョン・ムハ氏だ。昨年末に起こした訴訟だったのではなかったか。しかし今回、プラハ第一地裁は意表な判決を下した。常設展示するための固有の施設を用意することが条件であったと解釈されるが、それが満たされていないのだから、譲渡は無効である──という論法で、プラハ市の所有権を否定したのだ。ではいったい、9年前のドナドナは何だったのか。言わずもがな、プラハ側には不服で、不当判決であるとしている。
プラハ市庁はいぜんから、ムハの後援者であったチャールズ・リチャード・クレインから寄贈された、とも主張していた。がんらい《叙事詩》の制作を依頼したのも、所有したのもこの米国人であり、ムハは画家として制作を請け負ったにすぎず、作品を所有していたわけではないから、遺族とて相続する権利など生ずるはずもなかったのだと。とはいえ、法廷戦術にすぎぬ方便に、行政の真意をさぐるのはナンセンスであろう。というのも、市側は並行して、画家との契約の条件も履行しようとしている……すくなくとも、そういう態度をとっているのだから。
同市は、《叙事詩》展示施設について、いまだ準備中であると表明している。なにしろ全20幅のモニュメンタルな大作で、寸法にすると横に広いものは8,1メートル、高さは高いもので6,2メートルにおよぶというから、都合するのに手まどるというのはわかる。しかし、9年はながい。以前、プルゼニュ市の博物館施設の件でも触れたように、怠慢なのか不作為なのか、チェコ共和国の行政にはよく聞かれる話ではあるにせよ。
それでも秋口の報道では、プラハ市内に7か所ほど候補地が挙がっており、うち3つの箇所について有望視されている由であった。それが、パンクラーツ広場、サヴァリン宮、ブラーニーク製氷所だったようだ。むろん検討するだけなら誰にでもできるとはいえ、訴訟手続きのてまえ、本気度を示す必要があったためか、この討議にはムハのご遺族にも加わってもらっている旨つたえられていた。
遺族といっても件のジョン・ムハ氏を想定するのは、われら読者にとって無理があろう。それだから、これはヤルミラ・ムハ・プロツコヴァー氏のことではないかと思われている。アルフォンス・ムハのもうひとりの孫であり、故イジー・ムハの娘にあたる。報道の文言にみる「nevlastní」とは、双方が異母きょうだいであることを意味してはいるが、一説にはジョン・ムハ氏には亡父との血のつながりもないとも言われており、ひょっとすると世論がプラハ市側の支持にかたむきがちになるのも、たんなる排外的愛郷意識だけでなく、このあたりにも背景があるのかもしれない。控訴を準備するプラハ市としては、今回の訴訟がながびくならば、両者の相続についての別件の法廷闘争を蒸し返すことで劣勢の挽回をはかるかもしれない、と虚仮おどしめいた情報をリークしている。
ビロード革命ののち、作品群についてよく研究され、整理され、また修復され、美術館にそれを閲覧できるのもありがたいことではある。そのおおくは故イジー・ムハに負っているといわれているが、ジョン・ムハ氏とて実母とともにムハ財団を設立して、作品の保全や公開にあたってきた。結局のところ、一般の愛好家たちからみれば、状態よく保管され、妥当なやり方で公開してもらえれば、だれが所有していてもあまりかわらない。ただし、だれもが権利を主張するいっぽうで、作品が死蔵される状態におちいるならば、さまざまな意味で損失となる。これは関係者にも認識されているにちがいない。
宙ぶらりんの所有権はともかく、《叙事詩》は2011年以降、美術館の保管庫でプラハ市が管理してきた。それが昨年10月、企画展への貸し出しという名目で、古巣のモラフスキー・クルムロフに5年間の年限で貸与されることが承認されたのも、道理である。そして、この時限がプラハ市側にとっては、展示施設を設ける猶予期間となる。とはいえ、係争中の現状であってみればプラハ政界にも異論があるらしく、ANO党などは、一時貸与というが恒久の移管になりかねないと懸念を表明していた。いっぽうのクルムロフ側は、どんな判決が下されようが関係ないと、つい先週の報道でも鼻息が荒かった。
ふたたび展示会場となるモラフスキー・クルムロフの邸第では、貸与の条件とされた展示空間の改修がすすめられており、年末には《叙事詩》が搬入され、来年2月か3月には開場されるという見通しが示されている。10年前は荒廃してはいたが、この機会に空調までもあらたに整備されたくらいだというから、ちょっと見てみたい気がする。もともと壁のスタッコも分厚く、おそらく温度管理や吸湿にも利があった。かつてナポレオンも訪れたという由緒ある建物だ。5年といわず、そのまま置いといてやってもいいじゃないか、と思ってしまうのである。なにより、画家の望んだ威厳がたもたれている。
もっとも観光業界にしてみると、モラフスキー・クルムロフでの展示は不利である。功利主義的な建て前じょう、人類の至宝をなるべく多くの人にみてもらうのが理想であるとするならば、観光客にとってアクセスが不便というのは、悪である。ただ、地元側が主張するように、ウィーンの観光客を取り込むことを想定するなら、多少は地の利もありそうだ。直線距離では100キロほどで、車ならばミクロフ経由かズノイモ経由、列車ならばブジェツラフ経由か、あるいはブルノ経由となる。とはいっても、移動に3時間ほどはみておかねばなるまい。直線200キロのプラハからでも2時間半かそれ以上、列車では4時間ちかくはかかることを思えば、やはり辺鄙にはちがいない。
なお、フランス語ふうの「ミュシャ」という表記のほうが普及しているだろうことは存じ上げている。この点、ロンドン生まれのジョン・ムハ氏は英国暮らしがながく、もとより御母堂がスコットランドのひとということもあって、とうぜん英語でもインタヴューに応じるが、聞き手が「ムーカ」と発音しても、咎めたりはしない。けれど、しぜんに応答するなかで「……アルフォンス・ムハ!」と、ただしい訓みをさりげなく強調することもまた忘れない。
*参照:
*上掲画像はWikimedia













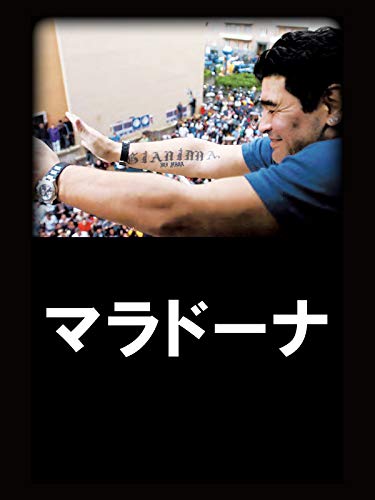







![[まとめ買い] 初版 金枝篇 [まとめ買い] 初版 金枝篇](https://m.media-amazon.com/images/I/B1zD3huyy7S._SL160_.png)