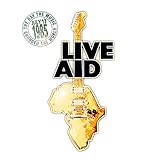大陸ヨーロッパでは、感染症対策の各種行動制限が緩和に向かいつつあり、そんな各地の動向を報じるメディアも多い。
NHKのニュースでは5月12日、ベルリーン在住の多和田葉子とのインタヴューが放映された。いまや全米図書賞受賞作『献灯使』が書店ではしきりに推されているが、初期の『犬婿入り』も面白かった。所収の「ペルソナ」や、あるいは別の短篇「ゴットハルト鉄道」なども身につまされるところもあって、愛着がある。
多和田はベルリーン市内の様子を伝え、また、危機対応の遣り様から支持率が8割にまで上昇しているというアンゲラ・メルケルについて「理系のお母さん」というふうに紹介した。トランプを暗示する「威張ったお父さん」との対比もよかった。もともとブンデスカンツラー(連邦宰相)をもじって、ブンデスムター(連邦の母)と呼ぶひともあったくらいで、納得がいった。そういえばモラヴィアの酒場で会ったŠ氏などは、財布にメルケルの写真を忍ばせていたものだった。しばらくのちには持ち歩くのをやめてしまったが。ヒトラーという歴史的なトラウマから、カリスマが信用されない風土とはいうものの、政治家としてというよりも、人品骨柄からして長期政権を維持してきたくらいの人気はやはり元からあるのだ。
報道を追ってきたかぎり、各州政府からの突き上げに屈して、急に「緩和」に踏み切らざるを得なくなったようにも見えたが、これもいつもの母の豹変というやつである。移民政策しかり、原子力政策しかり……。有り体にいえば風見鶏だが、この「バランス感覚」がなかったならば、ここまで君臨することもなかった。そして、子らを守るために暮らしを変更してゆくとき、理由についても自然科学的に明快かつ説得的に言い含めることもわすれない母親、というのが多和田の印象なのだろう。
振り返ると、かつてイスラーム国のイデオロギーに毒されたジハーディストが世に跋扈していたころ、冬のベルリーンでアドヴェントの市が標的になったことがあった。愛娘がかの地に住むという友人にすぐ尋ねれば、無事との返事であった。西欧の大都市に住むのも命懸けで、脅威はウィルスに替わったが、いまだに心配の種は尽きぬことだろう。
旅行で訪れるぶんには気楽でたのしいものだ。むかしの話である。学部の後半はヴァイマール文化の資料に首っぴきだったから、のち訪れてみると、見るものすべてが知識を確認するための装置のようにも思えた。啓蒙主義の時代からヨーロッパには、大学を卒えた若者が勉学の仕上げに旅行する習慣があったが、卒業旅行というのは本来そうしたものであろう。知恵も生半可な在学中に行ったのでは尚早で、さほどは愉しくなかったと思う。
けっきょくヒトラーに投票したのは誰だったのか、という犯人捜しじみた研究は、戦後まもない時期からさかんであった。中間層、なかんづくホワイトカラー労働者が支持層の中心を成したのではないか、という説もまた早くからあった。それだから、ジークフリート・クラカウアーがルポルタージュに描きだした往時のサラリーマンなどは、とりわけ面白く読んだ。邦訳の書名も『サラリーマン』であった。ナツィを支持するに至った人びとはどのような生活をおくっていたのか、という興味は学問的なものであったにせよ、やはりどちらかといえば下世話なものであろうか。
クラカウアーといえば『カリガリからヒトラーまで』のほうが知られているけれども、だいぶ経ってから、その映画版というのを観る機会も得られたのは幸運であった。とまれ、文章の理解を補完してくれるのが視覚情報であることは、ふるくコメニウスの実践にも示されたとおりである。20世紀において典型的には活動写真、すなわち映画を意味した。たとえば 、マレーネ・ディートリヒが歌手を演じた『嘆きの天使』には、当時の労働者が余暇に好んで通ったというヴァリエテが描写されていたものだった。それを踏まえて、じっさいにポツダム通りの〈ヴィンターガルテン〉へ行って、拍手喝采する観衆のひとりとなってみると、百聞は一見になんとやらで、大小の疑問が氷解したものだった。とりわけ、当時のサラリーマンの気晴らしの実態がわかったことで、なんともいえない満足の感を得た。
それも、どうということはない。『ベルリン・天使の詩』を愛する映画ファンならば、むしろ〈ズィーゲスゾイレ〉を見て感涙するだろう。美術史やデザイン史を専攻したひとなら〈バウハウス=アルヒーフ〉であろうし、軍事史なら〈総統地下壕(の案内板)〉だ。観光の愉しみとは本来こういうもので、つい最近までは、アニメを観て育った欧州の若者が、同様の体験をもとめて日本に殺到していた。若いうちには旅をせよと世に言われる所以であろうが、コロナ世代はこうした学習の機会も奪われることになるわけか。
ただ正直なところ、観光や仕事でゆくならともかく、あの町に住みたいというほどの魅力があるかというと、自分には感じることができないようだ。どうせなら食文化のゆたかな南の諸州のほうがよいし、じっさいよかった。が、これも相対的なものだろう。つまり「行けば稼げますよ」などとそそのかされれば、急に魅力を感じるようになるとは思う。そんなものだ。
ということは、文豪たちには「あの町に行けば書けますよ」と何者かがささやくのだろうか。多和田葉子については何も存じ上げないが。芸術家は大都会に集まりたがるものではあるにせよ、文学者にとってはとくべつな町ではあるらしい。
端的な例といえば、最晩年のフランツ・カフカである。晩年といっても、結核にむしばまれ40歳という若さで絶命したカフカだ。1923年9月24日、重病をおしてベルリーンに移り住んだのは、ナポレオンのロシア遠征にも似た無謀な跳躍であった、と本人も述懐している。といっても、はじめて踏んだ地というわけでもなかった。たしか出張経験もあったし、一時期婚約していたフリーツェを訪ねたこともあった。身近な大都市だった。プラハでは現代ヘブライ語の個人レッスンを受けていたが、その教師役の女性が生物学を学ぶため転居した、というのもひとつのきっかけにはなっていた。
とはいえ、書けるわけでも稼げるわけでも何でもなかった。折しも戦後のハイパー・インフレに喘いでいたメトロポリスである。旧来の1兆マルクを1マルクとした、レンテンマルクが登場した年でもあった。じっさいカフカも困窮した。原稿用の紙を買うのもおぼつかず、電気やガスも止められて難儀した。
それでもドーラなる少女と暮らす途を選んだカフカに、瀕死の作家の壮絶な「けなげさ」を見る。シュテーグリッツ=ツェーレンドルフといえば今でこそ高級住宅街も擁するが、シュテーグリッツ地区にかぎれば、移民の割合もまた高い。そこで、ヘブライ語の書を朗読し合うなどして、遙かなパレスティナに思いを馳せ、つつましやかに暮らした。創作においては己に厳しいカフカのこと、草稿の多くを少女に焼却させているが、かろうじて「小さい女」「巣穴」といった小品がここで成立し、のちに日の目をみた。
けっきょく病状の悪化で、翌1924年の3月17日にはプラハに連れ戻された。連れ戻したのは親友のマックス・ブロートだった。自身がドイツ語訳を担当した、ヤナーチェクのオペラ『イェヌーファ』のベルリーン公演に合わせてやってきていた。しかしカフカは、ひと月もプラハに留まらなかった。4月7日には、ウィーンのサナトリウムへ出発したのだった。体重40キロ台にまで痩せ衰えたカフカは喉頭結核も併発し、嚥下すら困難となるなか、ビールやワインをのむ幻覚を見るほどに意識も混濁してゆく。とちゅう大学病院での高度な治療を経るも、戦局かならずしも好転せず、6月3日の白昼、郊外の別のサナトリムでついに没した。
件のドーラ・ディアマントを名乗った少女は、カフカの最期を看取った。のち女優として活躍したが、ドイツ共産党の幹部と結婚したのがまた艱難のはじまりで、遺品として私蔵していたというカフカの原稿がゲシュタポに押収されてしまった。なかには、知られざる傑作もあったかもしれぬ。あーあ。──以上は主に、エルンスト・パーヴェルによる伝記によった。
ところで「伯林」と表記したとたんに思い出すのが鷗外森林太郎であるが、あれは留学という名の軍務のために逗留したにすぎない。そうそう、ルイーゼ通りの〈森鷗外記念館〉にも行ってみたのは言うまでもない。近年には館内の改装がつたえられていたが、いずれにしても現在は閉鎖されているにちがいない。そういえば、先般クルーズ船へ派遣された陸自の隊員らにあっては、運用ノウハウのうちに、鷗外のもちかえった衛生学の知見を受け継いでいるのだろう。
*参照:















![桂 枝雀 落語大全 第二十八集 [DVD] 桂 枝雀 落語大全 第二十八集 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/5153AdZz42L._SL160_.jpg)






![チェコ産ロゼワイン カベルネ・ソヴィニヨン 2015-ROUGE [Z-7] チェコ産ロゼワイン カベルネ・ソヴィニヨン 2015-ROUGE [Z-7]](https://m.media-amazon.com/images/I/41524K6BpiL._SL160_.jpg)

![チェコ産ロゼワイン サンローレント 2018 [LAH2003] チェコ産ロゼワイン サンローレント 2018 [LAH2003]](https://m.media-amazon.com/images/I/31yfO-fLCKL._SL160_.jpg)

![チェコ産白ワイン ムシュカート・モラヴィア 2018 [LUD2001] チェコ産白ワイン ムシュカート・モラヴィア 2018 [LUD2001]](https://m.media-amazon.com/images/I/313qoALR9fL._SL160_.jpg)
![チェコ産赤ワイン アンドレ 2016 [LUD2002] チェコ産赤ワイン アンドレ 2016 [LUD2002]](https://m.media-amazon.com/images/I/31634nGJZ-L._SL160_.jpg)